
| 食・農・里の新時代を迎えて 新たな潮流の本質 |
|||||
| | 食糧危機 | 抗議運動や暴動 | 輸出規制 | 投機対象 | 食料自給率 | 食料安全保障 | 天保の飢饉 | | 米騒動 | ヴェルサイユ行進 | 控えめに振る舞う庶民 | 日本の米技術 | 農地と農業用水 | 片樋まんぼ | | カナート | 緑の革命 | 農林10号 | 食料消費構造の変化 | 畜産物の生産 | 日本の農業状況 | | 6次産業化 | 日本のドメーヌ | 金賞受賞 | グローバル化するワイン市場 | 世界の森林 | 日本の森林 | 森林の多面的機能 | 森林整備 | 少子高齢化 | まち・ひと・しごとの創生 | 人間の行った人間らしい革命 | | 啓蒙思想 | 文化に触れる | 参考情報 | |
|||||
| 災害がもたらす 食糧危機 |
|||
| 「干ばつの時の祈り」 ミャサイェドフ ワルシャワ国立美術館 | |||
2007年から2009年にかけて、オーストラリアの干ばつや ヨーロッパの天候不順の影響を受け、 小麦や米などの穀物価格は従来の3倍~4倍に高騰したといいます。 また、2012年にアメリカは深刻な干ばつに見舞われ、 大豆・とうもろこしの価格は市場最高値を更新したそう。 このような出来事は、世界では大きな話題となった一方、 日本では比較的話題にならなかったといわれます。 ○私たちの生涯|生と死の狭間にある「時」を歩む |
|||
| トップに戻る | |||
| 食糧をめぐり発生する 抗議運動や暴動 |
|||
| コートジボワールの暴動 | |||
2008年の穀物価格の高騰時には、 世界各国で食料をめぐる抗議運動や暴動が発生したといいます。 ○米(こめ)関係から発生した国 セネガル・ギニア・シウラレオネ・コートジボワール・カメルーン・ バングラデシュ・フィリビン・インドネシア ○麦(むぎ)関係から発生した国 チェニジア・モロッコ・モーリタニア・エジプト・ウズベキスタン・イエメン ○とうもろこし関係から発生した国 メキシコ・モザンビーク ○その他 ハイチ・ブルキナファソ・エチオピア・ソマリア |
|||
| トップに戻る | |||
| いざという時は自国内供給が優先 農産物の輸出規制 |
|||
| 東京港 青海コンテナふ頭 東京都港湾局 視察船「新東京丸」より 2016.08 |
|||
2008年、穀物の価格高騰を受けて、世界では広く輸出制限が行われます。 モロッコでは小麦・米の輸出ライセンス制導入(2008年7月~)、 レバノンでは小麦の輸出禁止(2010年8月~)、 エジプトでは米の輸出禁止(2013年11月~)、 ケニアではとうもろこしの輸出禁止(2008年9月~)、 インドネシアでは米の輸出禁止(2008年4月~)といったように、 食料需給のひっ迫や食料価格が高騰した場合には、 輸出規制により、自国内の食料安定供給を優先させていることが解ります。 また、自国内に余裕があったとしても、輸出によって国内価格への 影響があることから、制限を行っている場合が見られるそうです。 ※農産物の輸出規制の現状 農林水産省(2015年5月15日現在)、他より ○夢と希望を育む魅力ある街 臨海副都心 |
|||
| トップに戻る | |||
| 投機対象として注目される 穀物 |
|||
| シカゴ商品取引所(Chicago Board of Trade : CBOT) | |||
穀物価格の乱高下を受けて、穀物は投機目的で捉えらるようになり、 盛んに投資セミナーが行われているそうです。 画像はアメリカのシカゴにある商品取引所。 1848年に設立されたアメリカ最古の先物取引所で、特にトウモロコシや大豆など 穀物の先物価格形成に強みがあり、世界の穀物先物取引の多くが取引されているそう。 シカゴで先物取引が発達した理由は、そこがアメリカの穀倉地帯であり、 農産物の集積地だった背景があり、農家の人々はその年の作柄の良し悪し から生じるリスクを軽減する必要から先物取引が始まったとされます。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 先進国の中で最低水準 日本の食料自給率 |
|||
| 日清製粉鶴見工場|日本で最初に港湾部に建設された小麦サイロで、 備蓄基地としての機能も担っているそう|川崎市港湾局巡視船より |
|||
食料自給率とは、国内の食料消費が、 国産でどの程度賄えているかを示す指標だそうです。 主要先進国の食料自給率(カロリーベース)は、カナダ258%、オーストラリア205%、 フランス129%、アメリカ127%、ドイツ92%、イギリス72%となっており、 日本の食料自給率39%は、先進国の中で最低水準となっています。 ○未来に夢をのせて|持続可能な最幸のまち かわさき ○京浜工業地帯をつなぐ鶴見線 |
|||
| トップに戻る | |||
| 食料の多くを輸入に頼る日本 食料安全保障 |
|||
| 横浜港 本牧ふ頭BCコンテナターミナル | BC2管理棟 屋上より 2015.10 | |||
人間の生命を維持するために欠かすことのができない食料は、 人間の生きる上での楽しみでもあり、 健康で充実した生活を送るための基礎として重要な位置を占めています。 食料の多くを輸入に頼っている日本では、 国内外の様々な要因によって食料供給の混乱が発生する可能性があり、 そういった予想できない事態が起こった際にも食料供給が影響を受けずに 確保できるよう様々な準備をしているそうです。 ※食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)(抜粋) 第2条 (食料の安定供給の確保) 食料は,人間の生命の維持に欠くことができないものであり,かつ, 健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ, 将来にわたって,良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。 2 国民に対する食料の安定的な供給については, 世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ, 国内の農業生産の増大を図ることを基本とし, これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。 4 国民が最低限度必要とする食料は,凶作,輸入の途絶等の不測の要因により 国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し, 又はひっ迫するおそれがある場合においても, 国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう, 供給の確保が図られなければならない。 第19条 (不測時における食料安全保障) 国は,第2条第4項に規定する場合において, 国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは, 食料の増産,流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。 ※食料安全保障について 農林水産省 ○海運が支える日本の豊かな暮らし |
|||
| トップに戻る | |||
| 凶作により多くの人々が苦しんだ 天保の飢饉 |
|||
| 大塩平八郎像(菊池容斎作、大阪城天守閣蔵) | |||
江戸時代後期にあたる天保4から7年(1833~36)にかけて発生した天保の飢饉(ききん)。 日本全国は冷害に見舞われ食物が大凶作となり、米価が高騰して餓死者が続出。 各地で一揆や打ち壊しが起きたといわれます。 そのような中、大阪でも餓死者が続出したそうですが、 大坂東町奉行は対策を講ずることなく、大坂にあったお米を東京に運んだそう。 これに憤慨した陽明学者で元大坂東町奉行所与力であった大塩平八郎は、 飢饉で苦しむ民衆の救済と腐敗した幕政の改革を訴え、 門弟の武士や農民を率いて蜂起し、ここに大塩平八郎の乱が起こります。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 大正時代に起きた 米騒動 |
|||
| 焼き討ちされた岡山精米会社(1918年8月13日) (『画報近代百年史』第10集、国際文化情報社、1989年) 国立公文書館アジア歴史資料センター |
|||
第1次世界大戦中には、輸出激増に伴い物価、特に米価が高騰しましたが、 大正7年(1918)に政府がシベリア出兵の方針を固めたことを背景に、 投機目当ての米買い占めが起こり、米価が急騰します。 同年8月富山県の漁民・主婦などが、米の安売りを求めて、 県外への米の積み出しを阻止したり、米屋を襲うといった行動に出ます。 富山の騒動が新聞で全国に報道され、名古屋、京都、大阪、東京、広島など 全国各地に広がり、寺内正毅内閣は総辞職に追い込まれたそう。 この騒動は、大正デモクラシー期の護憲運動や普通選挙運動などに 影響を与えたといわれます。 ○独立自由の人格者を目指す大正デモクラシー |
|||
| トップに戻る | |||
| フランス革命の背景にある パン価格の高騰 |
|||
| ヴェルサイユ行進(10月行進・10月事件) | |||
市民革命の模範であるばかりでなく、 歴史上の一切の革命の模範とされる「フランス革命」。 その契機となった背景の一つには、 凶作(1787年)による食糧不足やパン価格の高騰があったとされます。 1789年10月、食糧難に苦しむ女性を中心としたパリ市民は、 国王ルイ16世をパリに連れてくれば、パンの価格が正常化すると考え、 パリからヴェルサイユまで約5時間かけて行進。 国王をパリに連行した際には、 「パン屋とパン屋の女房と小僧(王と王妃と王子)をつれてきたよ」と叫んだといいます。 ※フランス革命小史 河野健二 岩波新書 1959 第4章 王と議会と民衆 1789年-1891年 p90 ○私たちの身近に寄り添う「愛と人間性」の芸術|ミュージカル |
|||
| トップに戻る | |||
| Do you hear the people sing? - Les Miserables - | |||
| トップに戻る | |||
| 権力を尊く敬い、 礼儀を失わないよう控えめに振る舞う庶民 |
|||
| 東洋のルソーといわれた中江兆民(なかえ ちょうみん) 1847年-1901年 |
|||
※中江兆民 「東洋自由新聞」 明治14年4月 古(いにしえ)より民の乱を作(な)すは、 其(その)初め必ずしも乱を作(な)すことを欲するに非(あら)ざるなり。 蓋(けだ)し民なる者はその最も暴悍(ぼうかん)なるものといへども 自ら好みて乱を作すに非ず。 独(ひと)り乱を作すことを好まざるに非ずして乱を作すことを畏るるなり。 彼れその初め乱をなすことを畏れて、而(しか)して遂に乱を作すに至る者は何ぞや、 勢然(しか)らしむるなり。 勢なる者は人心の自然に発するといへども、 そもそも在上(ざいじょう)の人の力その多きに居る。 在上の人自らその勢を激して民をして乱をなすに至らしむるときは、 これ其(その)罪(つみ)民に在(あ)らずして在上の人に在るなり。 昔から庶民が反乱を起こすのは、 その初めから必ずしも反乱すること求めているからではない。 確かに庶民は最も荒々しいものといえるが、 自ら好んで反乱を起こすのではない。 単独で反乱するのを恐れているのではなく、権力を尊く敬い畏れているのである。 反乱を起こすことを畏れているにも関わらず、遂に反乱を起こすのはどうしてか、 勢いがそうさせるのである。 勢いは人の心に自然に発生するといえるが、 そもそも上にいる人の力が大きな原因となっている。 上にいる人が自らその勢いを激しくさせ、庶民が反乱に至る時には、 その罪は庶民にあるのではなく上にいる人にあるといえる。 ※斜字体はホームページ管理者の意訳 ○哲学からみた人間理解|自分自身の悟性を使用する勇気を持つ ○日本の権力を表象してきた建造物|日本人の自我主張 |
|||
| トップに戻る | |||
| 世界最高水準を誇る 日本のお米技術 |
|||
| コシヒカリ | |||
かつてお米の貿易は多くなかったといわれますが、 今日では世界に流通するようになっているそうです。 そのような中、日本のお米に関する品種改良、農機具、治水などの技術は、 世界最高水準にあるといわれます。 ○進化するテクノロジー 人間のフロンティア ○持続可能なモビリティ社会を目指して|日産追浜グランドライブ体験試乗 |
|||
| トップに戻る | |||
| 世代を超えた歴史的な財産 農地と農業用水 |
|||
| 関東平野の大開発に寄与した見沼代用水(埼玉県・東京都) | |||
日本では、2,000年以上の永きにわたり、人間の生存にとって不可欠な 食料生産の基盤である農地と水に連綿と手をかけてきたといいます。 農地と水利施設が整った現在、この歴史的な仕事は「保全管理」の段階に至っているそうで、 これらを良好な状態で次世代に引き継ぐことは大切な役割だと感じます。 ○水と共に暮らす|いつまでも美しく安全に |
|||
| トップに戻る | |||
| 江戸時代に作られた地下水路 片樋まんぼ |
|||
| 三重県いなべ市片樋地区|農林水産省より | |||
三重県いなべ市片樋(かたひ)地区に遺る地下水路、片樋間風(かたひまんぽ)。 江戸時代に作られた水路で、今もなお水田のかんがい用水として利用されているそうです。 「まんぼ」は江戸時代末期から大正時代に盛んに素掘りされたそうですが、 長さ1kmにも及ぶ片樋マンボは規模において他に類をみないといいます。 ○川とともに育まれてきた人々の暮らし|相模湾 江の島に注ぐ境川 |
|||
| トップに戻る | |||
| 繁栄を支えた背景の一つ 地下水路の建設 |
|||
| サファヴィー朝の古都 イスファハーン イラン 世界遺産 | |||
イランの首都テヘランの南約400kmに位置するサファヴィー朝の古都イスファハーン。 現在の人口は百数十万人を擁し、イラン第三の都市。 ユネスコ世界遺産に登録され、豪華で艶やかなペルシア絨毯など 多くの品々が並ぶバザールがある都市としても知られます。 イランのことわざに「イスファハーンは世界の半分」という言葉がありますが、 サファヴィー朝時代のイスファハーンは世界有数の都市だったそうです。 その繁栄の背景には、カナートと呼ばれる地下水路の建設があったとされます。 イランのような乾燥地帯では日照が強いので、 普通の水路では水源から農地に届く前に水が蒸発してしまうため、 ペルシア人は地下水路を建設したのだそう。 カナートの建設と維持には、莫大な資本と高度な技術を必要とし、 バザール商人たちはカナートに投資して、まず水主になり、そして地主になったそう。 こうして建設した農園からの収入がバザール商人をさらに豊かにしたといわれます。 ○寛大な統治により支配領域を広げた古代アケメネス朝ペルシア |
|||
| トップに戻る | |||
| 多くの人々の命を救った 緑の革命 |
|||
| 小麦畑 | |||
アメリカの農学者ノーマン・ボーローグ博士(Norman Ernest Borlaug, 1914年-2009年)は、 小麦の品種改良に努め、高収穫をもたらす品種(メキシコ小麦)を開発し、 メキシコを小麦輸入国から小麦輸出国に押し上げたといいます。 その後も世界各地で農作物の品種改良の指導を行い、 1960年代なかばに穀物生産量の驚異的増大をもたらした「緑の革命」の 中心人物となり、1970年には、世界の食糧問題に多大な貢献をしたとして ノーベル平和賞を受賞します。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 世界を救った日本の小麦 緑の革命につながる農林10号 |
|||
| 映画「NORINTEN~稲塚権次郎物語~」 2015年 | |||
1897年富山県南砺市(旧:城端町)の農村地帯に生まれた、 日本の農学者、稲塚権次郎(いなづか ごんじろう、1897年-1988年)。 育種家となった権次郎は、1935年岩手県農事試験場にて、 低い草丈で倒れにくく、成長が早く、収量が多い「小麦農林10号」を開発します。 それから数十年後の1960年代。世界では発展途上地域を中心に食糧難が深刻化し、 小麦など穀物の増産が急務とされた時代において、 ノーマン・ボローグ博士は小麦農林10号と交配した品種を誕生させます。 小麦農林10号の遺伝子を受け継いだ新しい品種は、 収量を増やすために肥料を使用しても丈が高くならず、 倒伏の危険がなく収穫の増加が見込める農林10号の利点が引き継がれ、 欠点であった熱帯地での生育が解消されたことから、 インドやパキスタンなどの多くの地域で栽培され、 飛躍的な小麦の増産へとつながったとされます。 権次郎の作った一粒の種は、ノーマン・ボーローグ博士の手によって、 多くの子孫を残し世界の農村地帯へと広まっているそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 映画「NORINTEN~稲塚権次郎物語~」予告編 1分45秒ver. | |||
| トップに戻る | |||
| 食料消費構造の変化 米から肉と油へ |
|||
昭和40年と平成18年の食生活を比較すると、 米については、1日5杯だったものが⇒1日3杯、 牛肉については、月1回だったものが⇒月3回、 植物油については、1.5kgボトルで年3本だったものが⇒年9本になるなど、 食生活が大きく変化してきいることが伺えます。 日本の食料自給率の低下の要因は、国内生産の縮小というよりも、 食生活の大きな変化により、国内で自給可能な米の消費量が減少する一方、 国内で生産が困難な飼料穀物や油糧原料(大豆、なたね)を使用する畜産物や 油脂の消費が増加したことが大きな原因だといいます。 一般に食生活の変化は、米からパン(小麦)に変わったと捉えらがちだそうですが、 実際には米から肉と油に変わっているそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 多くの穀物が必要となる 畜産物の生産 |
|||
| 福島県の畜産農家 2015.09 撮影 | |||
畜産物1kgの生産に必要な穀物量は、 牛肉では11kg、豚肉では7kg、鶏肉では4kg、鶏卵では3kgが必要なのだそう。 牛肉の値段が豚肉や鶏肉と比較して高いというのもうなずけます。 画像は福島県にある畜産農家で撮影した牛。 ここで飼われている牛は原則、出産可能なメス牛のみで、 オス牛の精子を購入してきて出産させるブリーダーの役割を担っているそうです。 生まれた子牛は数年育てられ後、全国の畜産農家に売られ、 各地でブランド牛として育てられるのだそう。 ちなみに、日本人が肉を恒常的に食べるようになったのは明治維新後だそうで、 所得が多くなると肉を食べる機会が増加するといわれます。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 日本の農業状況 農業従事者の減少と高齢化 |
|||
| 「晩鐘」 1857-1859、ジャン=フランソワ・ミレー オルセー美術館 | |||
平成7年における農業従事者数は256万人、平均年齢59.6歳であったのが、 20年後の平成27年には175万人、平均年齢67.0歳と、 人数の減少、高齢化が顕著になっています。 食市場に関しては、今後、日本の人口は減少する一方で、 65歳以上の老齢人口の割合は大きく増加し、大きな拡大は見込めないといわれます。 その一方、2010年に69億人といわれる世界人口は、 2050年には96億人に達する見通しで、 近年、経済成長がめざましいブラジル、ロシア、インド、中国等の新興国は、 大きな人口を擁しており、拡大する世界の食市場は、日本の農林水産物、 食品のマーケットになる可能性を秘めているそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 生産・加工・流通を一体的に展開する 6次産業化 |
|||
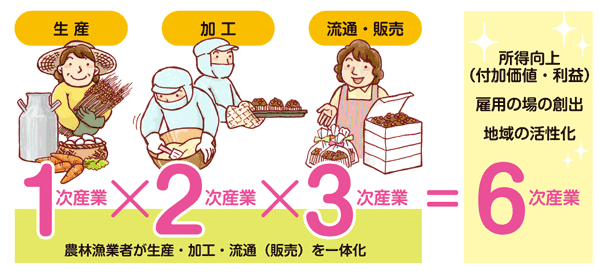 |
|||
| 政府広報オンラインより | |||
1次産業である「生産」、2次産業である「加工」、3次産業である「流通(販売)」 を掛け合わせて、より大きな付加価値を発揮する6次産業化。 農林漁業の6次産業化とは、農林漁業者が主体となって、 農林水産物の生産だけでなく、加工・販売まで一体的に事業を展開することにより、 農産漁村の所得向上、雇用の増大、地域の活性化を図る取組みのことだそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 世界に通用する 日本のドメーヌをめざして |
|||
| 中央葡萄酒㈱ 明野・ミサワワイナリー(山梨県) 横浜商工会議所 青年交流会 先進事例視察研修会 2016.09 |
|||
フランス語のドメーヌ(domaine)は、ぶどう園と醸造設備を持ち、 ぶどう作りからワインづくりまでを一貫して行うワイン醸造所のこと。 山梨県明野エリアに農場とワイナリーを構える中央葡萄酒㈱では、 ぶどう栽培管理は自社のワインを知るワイナリースタッフが徹底して行い、 収穫したぶどうをワイナリーで速やかに仕込むことで、 良質なぶどう酒を追求しているそうです。 ○豊穣の秋|ぶどう と ワインの里 山梨県勝沼 ○いちばん美しい夏に出会う|自然と文化の宝庫 信州 |
|||
| トップに戻る | |||
| 日本のワインとして 初めての金賞を受賞 |
|||
| 中央葡萄酒㈱ 明野・ミサワワイナリー(山梨県) 横浜商工会議所 青年交流会 先進事例視察研修会 2016.09 |
|||
世界約90ヵ国で発売されているイギリスのワイン雑誌「デキャンタ」が主催する 世界最大級のワインコンクール、「デキャンタ・ワールド・ワイン・アワード」。 2014年、世界各国から1万5007銘柄が出品されたこの大会で、 中央葡萄酒㈱が醸造した白ワイン「キュヴェ三澤 明野甲州2013」が 日本のワインとして初めて金賞を受賞したそうです。 ○駆け足で通り過ぎる信州の秋 |
|||
| トップに戻る | |||
| グローバル化しているワイン市場 ニッポンのグレイスワインを目指して |
|||
| 中央葡萄酒㈱ 明野・ミサワワイナリー(山梨県) 横浜商工会議所 青年交流会 先進事例視察研修会 2016.09 |
|||
グローバル化しているワイン市場を背景に、 日本ワインも真価が問われる時代を迎えているといいます。 国際機関(O.I.V)で甲州種が登録され、 10年前には夢見ることすらできなかったロンドン市場への輸出も始まり、 世界のワイン法の規範であるEU規格を適用したワイン醸造が、 現実の世界になってきているそうです。 中央葡萄酒㈱では、日本固有の気象に対峙しながら、 ニッポンのグレイスワインとして認められるために、日々挑戦を続けているそうです。 ○新たな絆から夢が膨らむグローバル人材 ○旅人が歩いたかけらを拾いに|木曽路 馬籠宿・妻籠宿 |
|||
| トップに戻る | |||
| 陸地の3割を占める 世界の森林 |
|||
| 森林率トップはフィンランドの72.9% フィンランドの北極圏|森林とツンドラの原野が続く「ラップランド」 |
|||
地球の陸地に占める世界中の森林の割合は3割といわれます。 (産業革命以前は5割だったそう) 2010年現在、国土面積に占める森林の割合が大きい国は、 北欧の国フィンランドの72.9%。ついでスウェーデンの68.7%となっています。 ※Global Forest Resources Asesment 2010 (FAO) ○森と湖が広がる北欧の国 フィンランド|不屈の精神から新たな地平へ ○人類の未来を切り開く 地球深部探査船「ちきゅう」 |
|||
| トップに戻る | |||
| 世界有数の森林国 日本 |
|||
| 日本最大の湿原 釧路湿原 | |||
森林率が高いフィンランド、スエェーデンに次ぐ第3位は日本の68.5%。 日本は世界の中でも有数の森林国なのだそうです。 ○鶴の舞|釧路川キャンプ & カヌーツーリング ○カムイありて我あり、我ありててカムイあり|釧網線の旅 |
|||
| トップに戻る | |||
| 日本の国土の2/3を占め、 多面的機能をもつ森林 |
|||
| 立山・黒部 | |||
日本の森林は、国土の約2/3を占め、急峻な山間部に多く分布し、 降雨量が多く、南北に長く地形も複雑な国土のため 多様な森林帯が分布しているそうです。 また、日本の森林は天然林が6割、人工林が4割で、 森林資源の利用と再生という人間の働きかけを通じて現在の姿に至ったといいます。 森林は、水源涵(かん)養、山地災害防止/土壌保全、快適環境形成、 保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全、地球環境保全、木材等生産 といった多面的機能を通じて、国民生活・国民経済に貢献しているそうです。 ○天上につながる場所|北アルプスを貫く立山黒部アルペンルート ○いのち集まる流域 小網代の森|私たちが生きる地球の持続可能性 |
|||
| トップに戻る | |||
| 健全な森林のサイクル 森林整備の意義 |
|||
| 台風によって倒木した人工林 丹沢山地 神奈川県 | |||
森林の多面的機能の持続的発揮のためには、人間の働きかけによって 健全な森林を積極的に造成・育成する「森林整備」が必要なのだそう。 特に人工林では、「植える(植栽)→育てる(保育・間伐)→使う→植える」といった サイクルが機能して森林の再生を確保することが大切だといいます。 ○丹沢の自然をもっと身近に|自然再生の現場を訪ねて ○相模湾を見渡す新緑のプロムナード|丹沢 鍋割山・塔ノ岳 ○金太郎伝説が宿る|天下の秀峰 金時山 |
|||
| トップに戻る | |||
| 急激な人口減少・超高齢化に直面する 日本 |
|||
日本は急激な人口減少、超高齢化という課題に直面しているそうです。 日本の総人口は、今後100年間で100年前(明治時代後半)の水準に 戻っていく可能性があり、この変化は千年単位でみても類を見ない 極め急激な減少だといいます。 また、2025年には団塊の世代は後期高齢者となり、 2040年には全都道府県において人口減少。 現在、1人の高齢者を2.6人で支えている社会構造は、 2040年には1人の高齢者を1.4人で支える社会構造になると推定されています。 ○絆よ再び|高齢化率38%を超える大型団地が示唆するもの ○Discover Tomorrow|新たなスポーツ文化の確立 ○競技スポーツと生涯スポーツの融合を目指す|スポーツクラブ・マネジメント |
|||
| トップに戻る | |||
| まち・ひと・しごとの 創生 |
|||
| 中国・ベトナム・カンボジアなど多国籍の人々で踊る炭坑節 いちょう団地まつり 2015.10 (神奈川県横浜市) |
|||
※まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成26年12月27日閣議決定) ○基本的視点 (1)若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 (2)「東京一極集中」の歯止め (3)地域の特性に即した地域課題の解決 ○検討項目 (1)若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる (2)地方への新しいひとの流れをつくる (3)地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする (4)時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る (5)地域と地域を連携する ○個性を出し合いともに暮らせる「まち」 いちょう団地 |
|||
| トップに戻る | |||
| 人間の強さと弱さ、美しさと醜さをあわせもつ 人間の行った人間らしい革命 |
|||
| 「サン・キュロットの扮装をした歌手シュナール」 1792年 ルイ=レオポール・ボワイユ |
|||
※フランス革命小史 河野健二 岩波新書 1959 時代の流れというものは、とめようとしてもとめることができない。 私たちはたえず時の流れによって、無意味におしながされている。 民族の歴史も多くの場合、これと同じだろう。 革命は、民族が歴史におしながされるのではなくて、 精神の自立性をくっきりと歴史のなかでうちたてる作業である。 それは強烈な意志と行動のつみかさねである。このとき、 民族は無限の力を自覚し、あたかも時の流れはくいとめられたかのように見える。 社会の一切の関係、一切の価値は逆転し、強大なものは卑小(ひしょう)になり、 卑小なものは強大になる。こうして、民族は歴史の主体となり、 自己の存在を永久に世界史のなかにきざみつけるのだ。 1789年にはじまる10年間は、フランス人が世界史の主役を演じた時期である。 フランス革命と呼ばれるこの革命は、いわゆるブルジョア改革の模範で あるばかりでなく、歴史上の一切の革命の模範とされる。 しかし、この革命もやはり人間の行った革命である。 フランス革命を理想化するあまり、往々、見ることのできないものを この革命のなかに見たり、反対に見るべきものを見なかったりすることがある。 そういう偏見からはなれて、私はこの革命を 人間の行った人間らしい革命として見直すへきだと思った。 この革命は、人間の強さと弱さ、美しさと醜さを同時にふくんだものとして、 そしてその故にこそ模範的な革命として位置づけられる必要がある。 ○あるがままの生の肯定 フリードリヒ・ニーチェ ○苦しみに満ちている人間の生からの救済|ショーペンハウアー |
|||
| トップに戻る | |||
| 暗く覆いかぶさっているものを光で照らす 啓蒙主義 |
|||
| The Enlightenment Gallery(啓蒙主義ギャラリー) 大英博物館 Discovering the world in the 18th century |
|||
「啓蒙(けいもう)の世紀」と呼ばれる18世紀。 啓(けい)は「ひらく」、蒙(もう)は「おおう・くらい」とも読み、「暗く覆いかぶさっている ものを開く」ことを意味し、英語では「Enlightenment」と訳されています。 フランス革命は啓蒙思想を色濃く反映したといわれます。 ※フランス革命少史 河野健二 岩波新書 1959 第2章 啓蒙思想 Ⅰ啓蒙の世紀 p38 啓蒙思想は、社会内部のさまざまなの階級の動きや要求を反映し、 それを理論化したものである。優秀な頭脳と強い個性のみがそれをなしえた。 なぜなら、社会の諸階級といっても、それはなお形成途上であってたえず動いており、 その要求もまた複雑で漠然としていたから、それらを汲みとって原理的な体系に きたえ上げるためには、よほどの強靭な思索力が必要であった。 さらにまた、啓蒙思想は、同時に「批判の哲学」であって、 当時の一般的潮流に反対して、自己を主張する必要があった。 当時の一般的思想はキリスト教(カトリック)であり、国家主義であり、重商主義であったが、 これらはいわゆる「官許の(国が許している)学問」であって、権力の保護のもとにあった。 したがって、啓蒙思想は権力や、ときとして世論に反抗して、主張されなければならなかった。 出版が許可制で、著書は焚書(ふんしょ:書物を燃やされる行為)や入獄の 危険をおかさばならない時代であった。 少数の先駆者だけが、これらの試練にたえて、人類の精神史を飾ることができた。 ○人類の智の宝庫 大英博物館 ○与えられたものを無条件に受入れる世界 華氏451 |
|||
| トップに戻る | |||
| 人間の善だけでなく、人間の悪をも表現する 文化 |
|||
| 「言語の混乱(バベルの塔)」 ギュスターヴ・ドレ | |||
元外交官で元文化庁長官であった近藤誠一 先生。 「文化」のもつ役割には以下のようなものがあると指摘します。 ○感動、悩み、祈り、感謝の念の表現・共有 ○感動の持つ力、人間はロボットとは違う ○コミュニケーションや連帯といった社会的役割 ○経済的効果、地域振興、観光資源 ○個人に生きる力と幸福を与える 人間の善だけでなく、人間の悪をも表現する「文化」に触れることで、 人間は無心となり、自然体でいることができるよう。 日本再生のカギは「文化」にあるといいます。 ※私にとっての日本文化-その魅力と普遍性- 2011.07 文化庁長官(当時) 近藤 誠一 先生 第76回 円覚寺夏期講座 ○日本人の心を形成してきたもの|これからを生きる指針となるものを探る ○人間の心のあり方を理解する|日本人の精神性を探る旅 ○日系カナダ移民の歴史と日本人の精神性 |
|||
| トップに戻る | |||
| 参 考 情 報 | |||
○農林水産省ホームページ ○林野庁ホームページ ○JA全農(全国農業協同組合連合会) ○お米・ごはんに関する基礎知識 ○知っていましたか? 近代日本のこんな歴史|アジア歴史資料センター ○国立公文書館アジア歴史資料センター ○日本の歴史についてよく分かるサイト! ○学研キッズネット ○見沼たんぼのホームページ|さいたま市 ○JapanGov - The Government of Japan - ○Japan - The Government of Japan | Facebook ○GRACE WINE ○名著55 エミール:100分 de 名著 ○フリー百科辞典Wikipedia ○食・農・里の新時代を迎えて 2016.07 ・テーマ イントロダクション、グローバル化する社会の食料問題 わが国の食料自給力を考える 動き出した6次産業化、農産物輸出 森林資源と地域振興 東日本大震災からの復興~東北を再び 食料基地とするために~ 農山漁村の「宝」を活用した地域おこし 地域振興における広報・交流の力 総合討論 ・講師 末松広行 先生 経済産業省産業技術環境局長(元農林水産省農村振興局長) 小林厚司 先生 北陸農政局長 西経子 先生 農林水産省農村振興局農村政策推進室長 渡辺一行 先生 農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課 総括課長補佐 ・主催 放送大学渋谷学習センター ○「食糧危機」をあおってはいけない 川島博之 文芸春秋 2009 ○アファンの森の物語 C・Wニコル ○貿易実務 現場視察会 2010.06 川崎FAZ・横浜税関・本牧埠頭コンテナターミナル 主催 外語ビジネス専門学校 ○港湾活動と社会発展 横浜 2015.10 ・講師 池田龍彦 先生 放送大学神奈川学習センター所長・横浜国立大学名誉教授 ・内容 ・横浜港発展の歴史 ・港湾背後圏の発展と港湾活動 ・世界の海運の現状と貨物流動 ・開発途上国における港湾開発と経済成長 ・横浜港内見学(横浜市からの便宜供与を受ける) ・横浜港コンテナターミナル見学(南本牧埠頭地区) ・横浜港物流センター見学(大黒埠頭地区) ・横浜港見学を踏まえた補足授業 ・放送大学神奈川学習センター ○海から見る東京港 東京港探検クルーズ 2016.08 ・視察船 新東京丸 ・日本船主協会・東京都港湾局 ○多目的コンテナ船「Pacific IslanderⅡ」見学 2016.08 ・大黒ふ頭 ・NYKバルク・プロジェクト貨物輸送㈱ ・日本船主協会 ○畜産業の経営と現場視察 2015.09 「特産いしかわ牛」産地づくりモデル農家 福島県 ○第34回 日清オイリオ横浜磯子春まつり 2016.04 アマニ油と中鎖脂肪酸講座 講師 日清オイリオ研究所 担当者 ○横浜商工会議所 青年交流会 先進事例視察研修会 2016.09 中央葡萄酒㈱ 明野・ミサワワイナリー視察 ○水循環を知る-9月10日 下水道の日- 2016.09 神奈川水再生センター施設見学・横浜港海上見学会 主催 横浜市環境創造局、協力 横浜市港湾局 ○フランス革命とパリの民衆 ―「世論」から「革命政府」を問い直す 松浦義弘 山川出版社 2015 ○フランス革命小史 河野健二 岩波新書 1959 ○NHKスペシャル 神秘の大インド 第2回 天空の王国・ザンスカール 1991.10.14 |
|||
| トップに戻る | |||
Copyright (C) 2016 MOON WATER All rights reserved
