
 |
アンデス文明最後の国家 インカ帝国 地球や科学技術について紐解く国立科学博物館 |
 |
|||
| | クスコ | マチュピチュ | インティワタナ | 天体観測の水鏡 | ハイラム・ビンガム | ケロ | | キープ | アクリャ | カパコチャ | 滅びゆく帝国 | アタワルパの処刑 | 特別展 | 国立科学博物館 | | 上野恩賜公園 | D51 | 日本館 | フーコの振り子 | 天体望遠鏡 | 黒漆塗天球儀 | | 日本列島の生い立ち |誕生と絶滅の不思議 | 零式艦上戦闘機 | ミュージアム・レストラン | | Cafe | シロナガスクジラ | 参考情報 | |
|||||
| 聖なる谷 インカ帝国の首都だったというクスコ |
|||
| 世界遺産 | |||
15世紀前半から16世紀前半にかけて繁栄した、 アンデス文明最後の国家といわれるインカ帝国。 クスコは「へそ」を意味し、 インカ帝国(タワンティンスーユ)の首都だったそうです。 ○神秘な遺跡・情熱のタンゴ 多様な文化が交差する南米 ○時空を超える旅に出かける世界遺産 |
|||
| トップに戻る | |||
| 空中都市マチュピチュ | |||
| 世界遺産 | |||
標高2,400mほどにあるというマチュピチュ。 (ちなみにクスコは3400mほどだそう) マチュピチュとは「老いた峰」を意味するそう。 「空中都市」とも呼ばれるこの遺跡は、 スペイン人から逃れるために、あるいは復讐の作戦を練るために、 インカの人々が作った秘密都市だったともいわれているそうです。 ○Bon Voyage 地球一周の旅へ |
|||
| トップに戻る | |||
| 太陽をつなぎとめる石 インティワタナ |
|||
インティワタナは、「太陽をつなぎとめる石」という意味がある岩だそう。 日時計として使われたともいわれているそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 天体観測の 水鏡 |
|||
石の上に水を張り空を映し、 天体観測に使用されたのではないかと考えられているそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| マチュピチュを発見した冒険家 ハイラム・ビンガム |
|||
謎に満ちたマチュピチュは、今から100年ほど前の1911年、 アメリカ人探検家ハイラム・ビンガムによって発見されたそうです。 ハイラム・ビンガムは、 映画「インディジョーンズ」のモデルとされるそう。 ○インディ・ジョーンズ4 クリスタルスカルの王国 予告 YouTube |
|||
| トップに戻る | |||
| 互恵の意味があったという杯 ケロ |
|||
インカの人たちは男と女、右手と左手など身近にあるものから 「2つで1つ」のものが一番美しく安定していると考えていたそうです。 「2つで1つ」の遺物としては、ケロと呼ばれる杯が多く出土しているそう。 ケロには、互恵的な意味があったそうですが、 違う側面では、インカがある集団を征服した場合、 その集団の指導者に贈り物を与え(拒否することはできないそう)、 従うよう仕向け、心理的手法を用いた統治にも活用されたそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 文字の代わりに活用されたという キープ |
|||
インカは文字をもたなかったそうです。 15世紀前半から16期前半まで存在していたというインカ帝国。 日本でいえば室町時代から安土桃山時代頃でしょうか。 キープ(Quipu)と呼ばれる紐は、 結び目の数や位置、色などで数や文字を表したそう。 各地への王の命令は、 キープを持ったチャスキ(飛脚)がタンボ(宿駅)を中継して走り、伝えられたそうです。 ○旅人に人馬を提供した宿場、木曽路 馬籠宿・妻籠宿 |
|||
| トップに戻る | |||
| うるわしの乙女 アクリャ |
|||
| ケチュア族の女性 エクアドル・コタカチ | |||
インカの王は、 各民族に対して、インカ太陽神に仕える娘たちを要求したそうです。 アクリャと呼ばれる女性たちは、 容姿が美しく、賢く、織物が上手で、処女であることが条件だったそう。 うるわしの乙女アクリャは、 「アクリャ・ワシ(選ばれし処女の館)」と呼ばれる場所で過ごし、 「ママコーナ」と呼ばれる年老いた処女たちの厳重な監督のもとに、 太陽神のために毛をつむぎ、糸を染め、布を織り、酒を造る日々を送ったそうです。 ※写真はイメージです ○絶世の世界三代美女 ○総勢3,000人の女性が住んでいたといわれる大奥 |
|||
| トップに戻る | |||
| 太陽に捧げた美しい子供たち カパコチャ |
|||
| ケチュア族の可愛い子供 | |||
太陽神の国インカでは、 農作物の収穫をもたらしてくれる太陽は絶対的存在であり、 日が一番短い日、太陽が戻ってきてくれるようにと、 美しい子供を生贄に捧げたそうです。 ※写真はイメージです ○世界をつなぎ、未来を拓く 国際こども図書館 |
|||
| トップに戻る | |||
| スペインによって滅びゆく インカ帝国 |
|||
| マヨール広場にあるフランシスコ・ピサロ像 スペイン トルヒージョ マヨール広場 |
|||
16世紀前半、インカ帝国は、 スペインのフランシスコ・ピサロ率いる160人ほどの兵士に滅ぼされたそうです。 ○スペイン・ブルボン朝の王カルロス4世とその家族たち |
|||
| トップに戻る | |||
| 最後の皇帝 アタワルパの処刑 |
|||
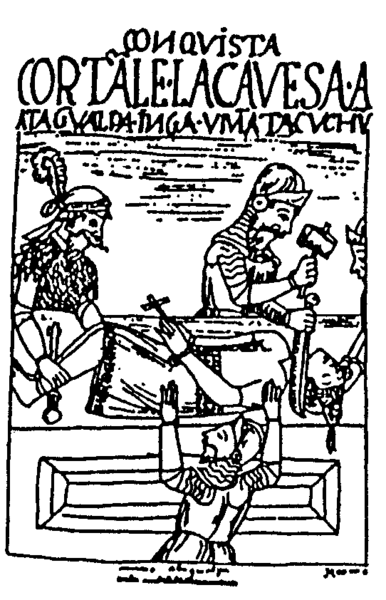 |
|||
| フェリペ・グアマン・ポマ・デ・アヤラによるというインカの記録 | |||
1533年、 スペイン人による「最後の皇帝」アタワルパの処刑のシーン。 インカ帝国の記録は、当時のスペイン国王フェリペ3世に宛てた フェリペ・グアマン・ポマ・デ・アヤラによる「新しい記録と良き統治者」が 貴重な資料となっているそうです。 ○江戸時代の処刑場 鈴ヶ森刑場遺跡 |
|||
| トップに戻る | |||
| たくさんの観覧者が訪れる 特別展 |
|||
とても人気のある特別展。 今回のインカ帝国展は、開幕から49日目で20万人を超えたそうです。 ○長蛇の列で賑わう東京国立博物館の特別展 |
|||
| トップに戻る | |||
| 地球や生命・科学技術の歴史について紐解く 国立科学博物館 |
|||
| 日本館は上から見ると飛行機の形をしているそう 重要文化財 |
|||
日本館は、 関東大震災による震災復旧を目的として昭和6年に完成したそう。 ネオ・ネルサンス調の建物は、上から見ると、 そのころの最先端の科学技術の象徴だった飛行機の形をしているそうです。 ○本物の作品で日本の文化史がたどれる東京国立博物館 ○西洋の美術をひも解く国立西洋美術館 |
|||
| トップに戻る | |||
| 上野恩賜公園にある 博物館 |
|||
| 国立科学博物館の入口 | |||
上野恩賜公園にある国立科学博物館本館。 本館には、日本館と地球館があるそうです。 また、港区白金台には附属自然教育園や、 茨城県つくば市には筑波実験植物園などがあるそうです。 ○文化の森 上野恩賜公園 ○自然の宝庫、白金台にある国立科学博物館付属自然教育園 |
|||
| トップに戻る | |||
| 蒸気機関車の代名詞となっている D51 |
|||
蒸気機関車の代名詞になっているというD51(デゴイチ)。 D51はたくさん製造されたそうで、 機関車1形式の両数では最大を記録しているそうです。 ○木曽路を走った蒸気機関車 C12 ○新橋SL広場の象徴 C11 ○国鉄最大の蒸気機関車 D52 ○夏を駆け抜けるSL函館大沼号 |
|||
| トップに戻る | |||
| ネオ・ルネサンス調の建物 日本館 |
|||
中央ホール上部などに使われているステンドグラスは、 日本のステンドグラス作品のなかでも傑作といわれるそう。 また、建物内外に使われている装飾性の高い飾りなどは、 戦後の建物には無く、この建物の見所だそうです。 ○ドイツ・ネオバロック様式の建物、法務省旧本館 ○アール・デコ様式を現在に伝える庭園美術館 |
|||
| トップに戻る | |||
| 地球が自転していることを証明したという フーコーの振り子 |
|||
1851年、フランスの物理学者レオン・フーコーは、 パリのパンテオン寺院で振り子を使った実験を行い、 地球が自転していることを証明したそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 日本で初めての本格的天体望遠鏡 トロートン天体望遠鏡 |
|||
日本で初めての本格的天体望遠鏡。 明治政府によって1880年(明治13年)イギリスから輸入・導入されたそうです。 内務省地理局観象台から東京天文台(のちの国立天文台)を経て、 長年のあいだ天文観測と天文教育に用いられたそうです。 ○フェルメールが描いた絵画、天文学者 |
|||
| トップに戻る | |||
| 江戸時代の天球儀 黒漆塗天球儀 |
|||
黒漆塗天球儀は、 江戸時代後期に製作されたと考えられているそうです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 日本列島の生い立ち | |||
「日本最古の化石」や「日本で初めて発見された恐竜」など、 日本列島のおいたちについて、学ぶことができます。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 地球環境の変動と生物の進化 誕生と絶滅の不思議 |
|||
約40億年前に誕生したという生命は、 大きく変動する地球環境の中で誕生と絶滅を繰り返して進化を遂げてきたそう。 「地球環境の変動と生物の進化 -誕生と絶滅の不思議」では、 その進化の道のりを垣間見ることができます。 ○地球形成の壮大なドラマ 神奈川県立生命の星・地球博物館 |
|||
| トップに戻る | |||
| 日本の航空技術を代表する戦闘機 零式艦上戦闘機 |
|||
| 科学と技術の歩み 地球館2F | |||
この零戦(ゼロせん)は、 1972年ラバウル北西ニューブリテン島沖の海底で発見され 引き上げられたものだそうです。 ○太平洋戦争のはじまり 真珠湾攻撃 |
|||
| トップに戻る | |||
| ミュージアム・レストラン ムーセイオン |
|||
地球館中2階にあるレストラン「ムーセイオン」。 ミュージアムの語源となったムーセイオンは、 ギリシア神話に登場する学術・芸術の女神「ムーサイ」(英語読み:Muse) の祀堂だったそうです。 ○古代の科学者や人文学者が一堂に会した「アテネの学堂」 ○鑑賞の余韻にひたりながらゆったり寛ぐミュージアム・レストラン |
|||
| トップに戻る | |||
| 観賞した後に休憩できる Cafe |
|||
| Cafeアトリエリーブ | |||
日本館地下1階ラウンジ内にあるCafe。 観賞した後、休憩するのにも丁度よいです。 |
|||
| トップに戻る | |||
| 最大の動物 シロナガスクジラ |
|||
最大の動物といわれるシロナガスクジラ。 これまでに30m以上の個体が確認されているそう。 国立科学博物館の出口付近にあるシロナガスクジラの模型は、 全長30mの巨体を海面から深く潜行させようとしている姿が再現されているそうです。 ○冬の沖縄の海に現われるザトウクジラ |
|||
| トップに戻る | |||
| 参 考 情 報 | |||
○国立科学博物館 National Museum of Nature and Science,Tokyo ○TBS インカ帝国展 マチュピチュ「発見」100年 ○ペルー観光公式ホームページ ○在ペルー日本国大使館 ○南米情報ムーチャスエルテ ○ペルー - ジェトロ ○ペルー気ままに一人旅 ○NHKスペシャル|失われた文明 インカ・マヤ YouTube ○アトリエ・ド・リーブ ○旅 時々 Photo ところにより にわか雨 ○フリー百科事典Wikipedia ○インカ帝国史 シエサ・デ レオン 増田義郎 訳 岩波文庫 ○インカに眠る氷の少女 ヨハン・ラインハルト 畔上司/訳 二見書房 ○失われたインカの都市 ハイラム・ビンガム Lost City of the Incas: The Story of Machu Picchu and Its Builders |
|||
| トップに戻る | |||
Copyright (C) 2012 MOON WATER All rights reserved
