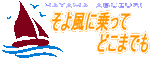「事実に基づく事」を阻害する要因
認知バイアス
 |
 |
 |
 |
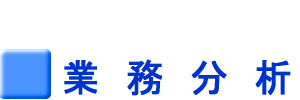 |
 |
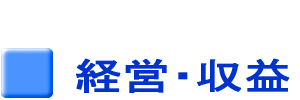 |
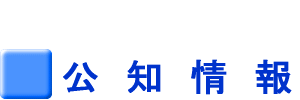 |
| 1.事実に基づき、厳密に構造化され、仮説主導であること |
当ページ「考え方・書式のご紹介」の中の「議事録のとり方」にも 記載しましたが、私は以下をとっても重視してきました。 ①事実に基づき ②厳密に構造化され ③仮説主導である この考え方を実態にあてはめてみると、 例えば、あるお客様にお伺いして過去のプロジェクト活動をお聴きすると、 総論としては成功したということになっていますが、 時間をかけてお話をしていく間に、 実態は意外とそうでもないということが多いように感じます。 なぜ、うまくいかなかったのかを改めて考えてみると、 事実(実態)を考慮しなかった事に本質的な要因がありそうです。 |
| 2.事実を歪める要因は? 認知バイアス |
人間は、ある事を評価するにあたって、 他の方の意見に影響受けたり、自分の利益や希望通りにしたいが為に 事実を歪めたりすることがありえます。 これを「認知バイアス」と呼びます。 認知バイアスは認知心理学や社会心理学の理論であり、 直感や先入観、恐怖心や願望が論理的な思考を妨げるのです。 |
| 3.認知バイアスの例示 |
①バンドワゴン効果 【強いものにはまかれろ!】 例えば、10人で会議をやっていた時に、一人ずつ意見を求められ、 最初の人から9人までが同じ意見をいった時は、 最後の人は違う意見を言いずらくなりますよね。 バンドワゴン効果は、 ある選択が多数に受け入れられているなど、 その選択への支持が一層強くなることを指します。 「バンドワゴン」とは行列の先頭の楽隊車のことであり、 「バンドワゴンに乗る」とは、時流に乗るとか、多勢に与するという意味があります。 ②リスキーシフト 【赤信号みんなで渡れば怖くない】 普段は穏健な考え方をし、比較的節度を守って行動することのできる人が、 大勢の集団の中では、その成員が極端な言動を行なっても、 それを特に気に掛けもせずに同調したり、一緒になってそれを 主張したりするようになっていくこと。 ③感情バイアス 【嫌なことは認めたくない】 たとえ相反する証拠があっても、 心地よい感覚をもたらす肯定的な感情効果のあることを信じたがる。 好ましくない、精神的苦痛を与えるような厳しい事実を受け入れたがらない。 ④アンカー効果 【初めに知っているか、知らないかで判断が変わる】 不確かな事態で予測や判断を行わなければならないとき、 初期値(アンカー)が判断に影響してしまうという心理的効果のこと。 買物をする時に、何と比較するかによって高いか安いかが変わってくる ことがあります。例えば、ある商品を購入しようとした時に、他店の方が 安い事を知っていたら、高いと感じます。 また類似商品と比較して高い・安いを判断している場合もあります。 ⑤確証バイアス 【自分の都合の良い事実しか集めない】 個人の先入観に基づいて他者を観察し、自分に都合のいい情報だけを 集めて、それにより自己の先入観を補強するという現象。 これも意外と多いと思いません? よく子供が「みんなもやっているよ」とか、「みんな持っているのだから」 と言っている事ってありますよね。 ⑥自己奉仕バイアス 【成功は自分の力、失敗は他人のせい】 成功は自分の手柄とするのに失敗の責任を取らない人間の一般的 傾向を表している。 それはまた、曖昧な情報を都合の良いように解釈しようとする 傾向として現れるとも言える。 例えば、自動車を運転する人の多くは、 自分が平均以上にうまい運転をすると思っているそうです。 ⑦認知的不協和 【もう聞きたくないから黙れ!】 人が自身の中で矛盾する認知を同時に抱えた状態、 またそのときに覚える不快感を表す社会心理学用語。 アメリカの心理学者レオン・フェスティンガーによって提唱された。 人はこれを解消するために、自身の態度や行動を変更すると考えられている。 ⑧コンコルド効果 【今やめたらすべて無駄になる】 ある対象への金銭的・精神的・時間的投資をしつづけることが損失に つながるとわかっているにもかかわらず、それまでの投資を惜しみ、 投資をやめられない状態を指す。 ⑨フレーミング効果 【表現の違いによる感じ方の差】 ある選択肢の判断を人が行う場合、その絶対的評価ではなく、 自己の参照点(基準点)との対比において比較されるため、 絶対評価とは異なる判断を導く可能性があるという効果のこと。 同一の選択肢であっても、選択者の心的構成(フレーミング)が異なると、 意思決定が異なってくる効果のこと。 ⑩バーナム効果 【占いがよく当たるわけ】 誰にでも該当するような曖昧で一般的な性格をあらわす記述を、 自分だけに当てはまる正確なものだと捉えてしまう心理学の現象。 ⑪ハロー効果 【後光か差す】 これは意外とよく聴く言葉ですよね。特に人事評価の場面などで 引用されることが多いような... ハローとは後光のことで、輝かしい肩書きや高い学歴などの、 顕著な特徴に引きづられて、その人のほかの部分や全体の 評価にゆがみがでることだそうです。 逆に、こういう人間だと言われると、実際にその通りなること をピグマリオン効果と呼びます。 ○ギリシヤ神話から名前がついたピグマリオン効果 ⑫あと知恵バイアス 【俺は最初からわかってたよ】 物事が起きてからそれが予測可能だったと考える傾向。 「起こりえたかもしれない別の事象」を検討することで、 このバイアスの効果を低減させられることが知られている。 |
| 3.マッキンゼー式世界最強の仕事術 |
①事実に基づき ②厳密に構造化され ③仮説主導である マッキンゼーに入社したばかりのアソシエート(入社間もないコンサルタント)が、 フォーチュン誌でトップ50社に掲げられているような企業の最高経営責任者 (CEO)と対峙する時、CEOは入社したての若者の言うことなど信用できないだろう。 信用できるのは、若者の言葉に圧倒的な事実の裏付けがあるからだ。 元マッキンゼー アンド カンパニーにいらした イーサン・M・ラジエル氏の著書「マッキンゼー式世界最強の仕事術」。 |
| 4.参考情報 |
1.Category:認知バイアス 【出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』】 2.認知バイアス 【出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』】 3.中学生からの論理的な議論の仕方 |